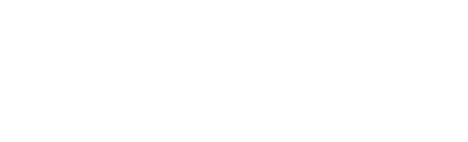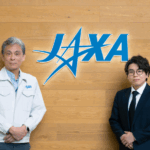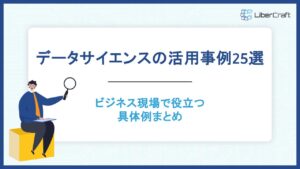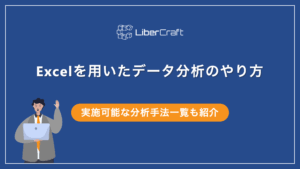BtoBマーケティングの現場では、成果が数値として見えても「なぜその結果が出たのか」を説明できない問題に直面するケースが後を絶ちません。属人的な判断や経験に依存した“感覚的なマーケティング”は、施策の再現性向上や効率化の妨げにもなっています。
株式会社Sells upは、センスや勘に頼るマーケティングを、データに基づいた「勝てる仕組み」へと変革させるプロフェッショナル集団です。クライアントのSFAやMAを活用したリード創出・商談化支援を行いながら、データドリブンな意思決定を実現する仕組みづくりを推進しています。
この取り組みの一環として、同社はリベルクラフトとともにデータ解析基盤の整備に着手。
わずか3ヶ月でAPI連携からクラスタリング分析までを実装し、これまで人手に依存していた数値分析の自動化を実現しました。
本記事では、株式会社Sells up 代表取締役の武田 大氏に、プロジェクトの背景や成果、そして今後の展望を伺いました。
PROFILE
プロフィール

武田 大 氏
株式会社Sells up 代表取締役
株式会社AOKIで接客業を、リクルートライフスタイル(現リクルート)で法人営業を経験。その後、株式会社ライトアップでBtoBマーケティングを担当し、デジタルマーケティングエージェンシーにて戦略設計や施策実行支援に従事する。2023年に株式会社Sells upを設立。BtoBマーケティングの戦略設計、リードジェネレーション、ナーチャリング、MA/SFA活用支援を中心に、業界・規模を問わず約80社を支援。Salesforce認定資格を複数保有。
三好 大悟
株式会社リベルクラフト 代表取締役 データサイエンティスト
慶應義塾大学で金融工学を専攻。卒業後はスタートアップのデータサイエンティストとして、AI・データ活用コンサルティング事業などに従事。その後、株式会社セブン&アイ・ホールディングスにて、小売・物流事業におけるAI・データ活用の推進に貢献。
株式会社リベルクラフトを設立し、AIやデータサイエンスなどデータ活用領域に関する受託開発・コンサルティングや法人向けトレーニング、教育事業を展開。

勘に頼らない意思決定へ。Sells upが挑んだデータドリブン改革の第一歩

今回の取り組みの背景について教えてください。
武田 大氏(以下、武田氏) 私たちSells upは、クライアントのSFAやMA(HubSpot、Pardotなど)を活用しながら、BtoBマーケティングにおけるリード獲得から商談化までを支援しています。
これまで、「CVR(コンバージョン率)の向上」や「商談数の増加」といった成果は出せていましたが、社内では「なぜその結果が出たのか」を明確に説明できない場面が多くありました。これにより、施策の再現性が担保できず、改善の方向性を議論する際にも根拠を示しづらいという課題にも直面していたんです。
SFAやMAに蓄積されたデータはツールごとに分断されていることも多く、「メール→Web閲覧→商談」といった顧客行動を一気通貫で追うことは簡単ではありません。さらに、各ツールのデータ収集や整形については、管理画面からCSVをダウンロードしてはコピー&ペーストを繰り返すといった作業に1ヶ月近くかかることもあり、とても非効率でした。
そこで、まずは“人力や感覚に頼らないマーケティング支援”を実現するために、学術的・統計的な視点から数字を説明できる仕組みをつくろうと考えました。数字の根拠を説明できれば、クライアントへの説得力も、社内の意思決定の速さも格段に上がると思ったんです。
データ解析の仕組みを構築するにあたって、協力先としてリベルクラフトを選定いただいた理由は何だったのでしょうか?
武田氏
当初は複数の候補企業にお話を伺いましたが、最終的にリベルクラフトさんにご依頼したのは、弊社が求めていた「統計」「AI」「文脈理解」の三拍子がそろっていたからです。データ分析の精度はもちろん、その分析結果をどうマーケティング施策へ落とし込み、現場で実行・検証していくかまでを一緒に考えていただける点が大きな決め手でしたね。
また、弊社が短期的な分析支援にとどまらず、“中長期的にAI活用へと発展できる支援”を求めていたこともリベルクラフトさんを選んだ理由の一つです。
三好大悟(以下、三好)
私たちとしても、単なる「データ分析代行」ではなく、“現場で自走できる分析文化”を根付かせたいという思いがありました。そのため、API連携による自動データ取得からRFE分析、クラスタリング、アソシエーション分析まで、3ヶ月で設計・実装することを今回のプロジェクトのゴールに設定しました。感じています。
API連携から統計分析まで。3ヶ月で築いた“データで動く仕組み”
今回のプロジェクトの概要を教えてください。
武田氏
プロジェクトは大きく3ステップで進めました。1ヶ月目は「データを自動で取得する」、2ヶ月目は「分析で使える状態に整える」、3ヶ月目は「攻めの分析に展開する」という流れです。
まず着手したのは、HubSpot・Pardot・SFAなど複数ツールのデータを自動で取得する仕組みづくりです。これまでは各ツールの管理画面を一つずつ開き、CSVをダウンロードしてはExcelにまとめていましたが、MAとSFAのデータが別管理になっていたため、どのタイミングでリードが離脱したのかを追うことも難しく、人的作業の負担がとても大きかったんです。
そこで、リベルクラフトさんのサポートを受けながら、APIとGAS(Google Apps Script)を連携させ、スプレッドシート上に自動でデータが集まる仕組みを構築しました。
三好
1ヶ月目に意識していたのは、「まずは“人が動かなくてもデータが取れる状態”を作る」ことです。具体的には、HubSpotやPardot、SFAなどの各ツールとGoogleスプレッドシートをAPIで接続し、GASを通じてデータを自動取得できるようにしました。
ただし、ツールごとに契約プランやAPI仕様が異なるため、同一コードでは動作しない場合もあります。そのため、各ツールの仕様に合わせてスクリプトを個別に調整し、取得エラーを回避できるよう設計しました。
武田氏
これにより、各ツールの最新データが毎晩自動でスプレッドシートに更新され、翌朝には最新の分析データを確認できるようになりました。従来はデータの取得まで1ヶ月近くかかっていたので、この仕組みを整えられたのは大きな前進だったと思います。

自動でデータが取得できるようになった後は、どのようなフェーズに進まれたのでしょうか?
武田氏
2ヶ月目は、取得したデータを「使える状態」に整えていきました。これまではデータを集めても整理や分析が追いつかず、「どの顧客が有望か」「どの施策が成果につながったのか」といった判断を、担当者それぞれの経験や感覚に頼る場面が多かったんです。
そこで導入したのが、RFE分析(Recency/Frequency/Engagement)です。RFE分析とは、顧客の最新行動(Recency)、接触頻度(Frequency)、関与度(Engagement)の3指標から、どの顧客が今最もアクティブかを定量的に把握する手法です。
この分析をもとに、リードの“温度感”を可視化し、スコアリングやステージマッピングを行うことで、リードが「興味」「検討」「商談」どの段階にあるかを明確にしました。
スコアリングでは、行動や属性ごとに点数を設定し、誰が見ても同じ基準で「優先度の高い顧客」を判断できるようにしました。ステージマッピングは、リードが購買プロセスのどの段階にいるかを分類し、営業やナーチャリングのタイミングを見極める指標として活用しています。
このルール設計によって、それまで担当者ごとに判断基準が異なっていたレポートが、スコアとステージに基づく統一基準で自動生成されるようになりました。
また、スプレッドシート上のデータは毎晩自動で更新されるため、常に最新の状態でデータの比較・評価を行えます。その結果、属人化が解消され、クライアントとの打ち合わせでも数字を共通言語として議論できるようになりました。
三好
この段階で重視していたのは「データの定義づけ」です。顧客によって、どのページを“エンゲージ”とみなすか、どの行動を分析対象とするかは異なります。
例えば、ある企業では「製品紹介ページの閲覧」が強い関心を示す行動だったとしても、別の企業では「事例記事の閲覧」のほうが指標になる場合もあります。
そのため、共通のスキームを一律に当てはめるのではなく、Sells upさんと相談しながら、クライアントごとに“何をエンゲージメントとみなすのか”を丁寧に定義していきました。
RFE分析やスコアリングでリードの状態が可視化された後、3ヶ月目ではどのような取り組みが行われたのでしょうか?
武田氏
3ヶ月目は、クラスタリング分析とアソシエーション分析という2つの手法を用いた、より高度な統計分析に着手しました。
クラスタリング分析では、似た行動傾向を持つ顧客を自動でグループ化し、「どんな顧客群が商談化しやすいか」「どんな行動が離脱につながりやすいか」を把握できるようになりました。
一方、アソシエーション分析は、「あるページを見た人が次にどのページを閲覧しやすいか」「どんな閲覧パターンが問い合わせや資料請求につながるか」といった行動の関連性を明らかにすることが可能となりました。
顧客の行動データから“傾向”を見える化されたのですね。
武田氏
はい、分析結果をもとに営業リスト上で顧客ごとの優先度が明確になりました。セールスチームは、時間に余裕があるときは“温度の低い顧客”にもアプローチし、繁忙期には確度の高いリードに集中できるようになっています。
以前は全リードに一律で架電していましたが、データに基づいて優先順位をつけられるようになったのは大きな進歩です。
ナーチャリングの手法も変わりました。これまでは「新しい記事が公開されたから配信する」といった自社都合の一斉メール配信が中心でしたが、今は「このページを見た人は次にこのページを閲覧する可能性が高い」といった行動データをもとに、先回りした配信ができるようになったんです。

三好
分析そのものの高度化のみならず、このフェーズでは“分析を現場のアクションに結びつけること”を目指しました。特にクラスタリングは、単なる分類ではなく「今どの顧客群が熱いのか」「どの顧客が離脱リスクを持っているのか」を示すことで、営業やマーケの動きを変えるための指標になります。
アソシエーション分析も、結果を報告して終わりでなく、「この傾向があるなら、次はこう動くべきだ」といった“攻めの活用”を意識しました。
こうした取り組みを通じて、Sells upさんのなかでも“データが現場を動かす”という感覚が定着しつつあると感じています。
“考える時間”を取り戻す。AIが運用し、人が意思決定する未来へ
プロジェクト全体を通じて、業務に大きな変化があったと推察します。
武田氏
3ヶ月の取り組みを経て、社内の意思決定スピードが大きく向上しました。マーケティングと営業の情報が一つの基盤でつながり、部門間の認識のズレも減ったことで、施策の改善サイクルも格段にスムーズになりました。
この仕組みを整えたことで、リソース配分にも余裕が生まれています。従来はレポート作成や集計に多くの時間を費やしていましたが、今では自社マーケティングにも注力できるようになり、「1日1本のコンテンツ発信」にも挑戦しています。
さらに、従来から行ってきたMA活用を軸とした一貫支援の質も、大きく高まりました。データの可視化や分析プロセスの自動化により、提案の根拠や施策検証の精度が向上し、クライアントのLTV(顧客生涯価値)向上にもつながっています。
結果として、長く信頼関係を築けるパートナーシップが育ちつつあるのは大きな成果ですね。

三好
Sells upさんのように、リード獲得からナーチャリング、営業支援までを一気通貫で担う企業は、データ活用の効果が特に出やすいと感じます。今回の仕組み構築によって、どの段階でどんな施策が成果につながったのかを“点”ではなく“線”で捉えられるようになったのは大きな進歩だと思います。
今後は、どのような展望を描かれているのでしょうか?
武田氏
今回のプロジェクトは「分析基盤を整える」段階でしたが、ここからは“分析結果を自動で動かす”フェーズに進めていきたいと考えています。MA/SFAの分析自動化はもちろん、広告予算の配分や媒体別の効果最適化、クリエイティブの評価(バナーやLPのCTR・CVR解析)、さらには解約リスクの予測や自動フォローまで、すべてをAIで運用する構想を描いています。
AIに任せられる部分はどんどん任せて、人は“考えること”に専念する。そんな状態を実現できれば、私たちの支援モデルもより再現性の高いものに進化すると考えています。
三好
AI導入を目的にするのではなく、「自分たちの業務のどこにAIを活用すれば価値が最大化できるか」を考えることが重要だと思います。単なる自動化ではなく、AIを“意思決定の補助輪”として使いこなす。この考え方こそが、長期的にデータ活用を成功させるためのポイントになると感じています。