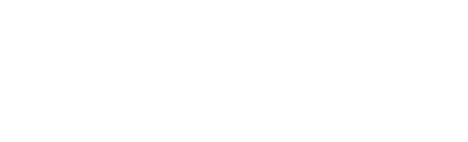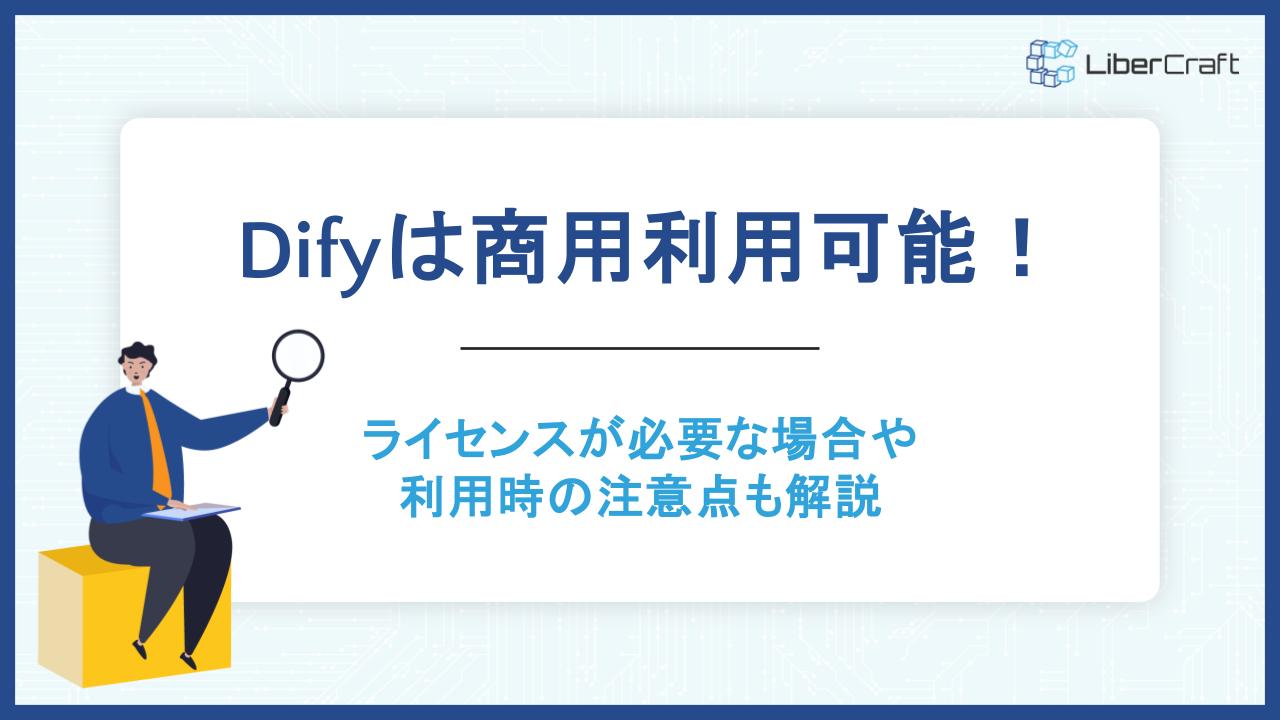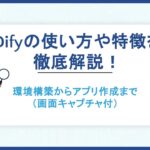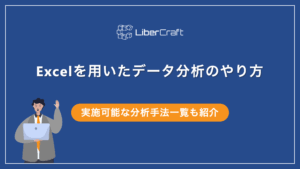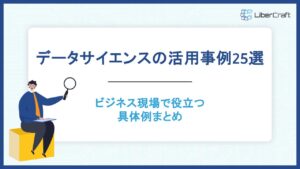「Difyを業務やサービスに導入したいけれど、商用利用しても大丈夫なのか」「ライセンスの取得が必要なケースがあるのか分からない」と悩んでいる方は多いのではないでしょうか。
Difyは、誰でも使いやすいオープンソースのAIアプリ開発プラットフォームで、ChatGPTなどの大規模言語モデルを活用したアプリをノーコードで構築できるのが特徴です。無料で試せる手軽さがある一方で、商用利用を行う場合にはライセンス条件の確認必須。
特に、企業内での導入や外部サービスとしての提供を検討している場合、利用形態によってはライセンスが求められることもあります。
そこで本記事では、
- Difyは商用利用ができるのか
- 商用利用にライセンスが必要な場合
- ライセンスの取得が必要な場合
について、わかりやすく解説します。
「Difyを業務に導入したいが、商用利用できるかわからない」「ライセンス取得など面倒」という方は、リベルクラフトへご相談ください。
リベルクラフトでは、Difyの導入支援だけでなく長期的に運用・業務で活用できるように支援します。お気軽に無料でご相談ください。
⇨リベルクラフトへの無料相談はこちら
Difyは基本的には商用利用できる
結論から言うと、Difyは基本的に商用利用が可能です。世界中の誰でも、無料かつ永続的にソフトウェアを利用・改変・配布できる権利が与えられています。
つまり、企業が自社サービスに組み込んだり、Difyを使って独自のAIアプリを開発・販売したりすることも可能です。以下はDify公式サイトから引用した商用利用に関する原文です。
【原文】
Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.
【日本語訳】
本ライセンスの条件に従い、各貢献者は、本作品および派生作品をソース形式またはオブジェクト形式で複製、派生作品の作成、公開表示、公開実行、サブライセンス、配布するための、永続的、全世界的、非独占的、無償、ロイヤリティフリー、取消不能の著作権ライセンスをお客様に付与します。
引用:Apache License 2.0
もう少しわかりやすく言えば、「自由に使っていいけれど、ライセンスの条件は守ってください」というルールです。
Apache License 2.0では、著作権の表記やライセンス文の記載を残すことが求められていますが、それ以外に商用利用を制限するような条件はありません。そのため、Difyを活用して社内業務を効率化するツールを作るのも、顧客向けのAIサービスを開発するのも問題ありません。
では、実際にどのような場面で商用利用できるのか2つのパターンで紹介します。
① 自社の業務効率化ツールとして活用する場合
Difyは、社内システムや業務支援ツールとして商用利用することが可能です。たとえば、営業資料の自動生成やFAQ対応チャットボットの構築など、業務を効率化する目的でDifyを導入しても問題ありません。
社内向けの利用であっても、Difyを活用して作成したアプリやワークフローは「商用利用」に該当しますが、Apache License 2.0では制限していないため、追加費用や申請なしで利用できます。
自社のデータや業務フローに合わせてカスタマイズすることで、AIの導入効果を最大化できる点は魅力です。
②顧客向けサービスや製品として提供する場合
Difyを使って開発したAIアプリを、外部の顧客に販売・提供することも認められています。たとえば、DifyをベースにしたAIチャットボットを自社ブランドとして提供したり、Difyの機能を組み込んだWebサービスを有償で販売したりするケースも商用利用の範囲に含まれます。
Apache License2.0では、ソースコードを改変したり独自機能を追加した上で再配布することも自由に行えますが、その際は「ライセンス表記を残す」などの基本ルールを守る必要があります。
正しくライセンスを遵守すれば、ビジネス用途でも安心して活用できます。
Difyの商用利用にライセンスが必要な場合
一方でDifyの商用利用にライセンスが必要な場合もあります。同様にDifyの公式サイトでも明言されています。
Dify(ディファイ)は、商業目的で利用することが可能です。
たとえば、次のような使い方が認められています。
・他のアプリやWebサービスのバックエンドとしてDifyを使う
・企業が社内向けのAIアプリ開発プラットフォームとして利用する
ただし、商用ライセンスが必要になるケースがあります。
それが、以下の「a. マルチテナントサービス」と「b. ロゴ・著作権情報」の項目です。
a. マルチテナントサービスとは?
「マルチテナントサービス」とは、1つのDifyシステムを複数の顧客(利用者)で共有して使うサービスのことです。
たとえば、SaaS型のAIアプリ構築サービスをDifyをベースに提供するような場合が該当します。
このようなマルチテナント環境を運営することは、Difyの運営元から書面で明示的に許可を得ない限り禁止されています。
つまり、Difyを使って他社に向けたSaaSや複数クライアント向けのAIサービスを作る場合は、正式な商用ライセンス契約が必要です。
b. ロゴや著作権表記を消してはいけない
Difyの見た目の部分(フロントエンド)を利用する際には、ロゴや著作権情報を削除・変更してはいけません。
たとえば、Difyの管理画面(コンソール)やアプリケーション画面から「Dify」のロゴを消す、または別の名前に書き換える行為は禁止されています。
ただし、Difyのフロントエンドを使わない場合はこの制限は適用されません。
出典:Difyライセンス
商用利用にライセンスが必要な場合は、以下2つです。
- マルチテナントで商用利用する場合
- ロゴ・著作権情報の削除や変更をする場合
マルチテナントで商用利用する場合
Difyを使って「複数の企業やユーザーが共有するSaaS」を構築・提供する場合は、商用ライセンスの取得が必須です。これは、Difyを「自社だけで使う」のではなく、「他のユーザーにも使わせる」形で提供するため、商用利用の範囲が広がるからです。
なお、マルチテナントとシングルテナントについては以下の表を参照ください。
| 項目 | マルチテナント | シングルテナント |
|---|---|---|
| 定義 | 複数のユーザー(企業・個人)が1つのシステムを共有して利用する形態 | 1つのユーザー専用の環境としてシステムを利用する形態 |
| 例 | Google Workspace、Salesforce、Microsoft 365 | 専用サーバー型のERPや自社専用のAIツール |
| ワークスペース数 | 複数(共有環境) | 1つ(専用環境) |
Difyにおける「マルチテナント」とは、複数のワークスペースを作成・運用する構成を指します。 たとえば、A社・B社・C社がそれぞれ異なる環境で同じDifyアプリを利用できるようにした場合、これはマルチテナント運用に該当します。
なお、複数のワークスペースを作れるのは、エンタープライズのみです。
エンタープライズプランのみが対象
先述した通り、Difyで「複数のワークスペースを作れる」のはエンタープライズプラン限定の機能です。そのため、無料版やスタンダードプランのユーザーは、そもそもマルチテナント運用を行うことができません。
つまり、通常のユーザーが1つのワークスペース内で業務ツールや顧客対応AIを使う範囲であれば、商用ライセンスを意識する必要はありません。
「他社にも同じ環境を提供したい」といったSaaS事業レベルの展開を行う場合のみ、Difyへの問い合わせ・契約が必要になります。
ロゴ・著作権情報の削除や変更をする場合
もう一つの注意点は、Difyのロゴや著作権表記を削除・書き換える場合です。 Difyはオープンソースとして誰でも利用できますが、表示されている「Powered by Dify」などのロゴや著作権情報を改変する行為は、商用利用の条件外になります。
たとえば、自社ブランドでAIチャットアプリを提供するために、
- Difyのロゴを削除
- 自社ロゴに置き換えたりする
と言った場合は、Dify運営への申請と商用ライセンス契約が必要です。
ただし、ロゴが表示されないバックエンド利用であれば、ロゴ削除や表記変更の問題は発生せず、ライセンスを取得せずに商用利用が可能です。
Difyの商用ライセンスの取得方法
Difyの商用ライセンスの取得方法について4つのステップで解説します。
- 自社の利用形態を整理する
- Dify公式へ問い合わせる
- ライセンス条件の確認・調整
- 契約締結と運用開始
1.自社の利用形態を整理する
まずは、「自社がどんな使い方を予定しているのか」を明確にしましょう。Difyはオープンソースとして誰でも使えますが、利用の仕方によってはライセンス契約が必要になります。
整理しておくべき主な項目は以下の通りです。
| 確認項目 | 内容の例 |
|---|---|
| 利用形態 | 社内利用のみor顧客提供型サービス(SaaS) |
| ワークスペース数 | 1つのみor複数(複数ならマルチテナントに該当) |
| ロゴ・著作権 | Difyのロゴを残すor削除・変更する |
| 想定ユーザー規模 | 利用予定のユーザー数、アクティブ数 |
| 開発環境 | クラウド(AWS・Azureなど)orオンプレミス |
| 目的 | 社内効率化、外販サービス,再販など |
この整理ができていれば、問い合わせ時にスムーズにライセンス判断をしてもらえます。
2.Dify公式へ問い合わせる
次に、公式の問い合わせ窓口から連絡を行います。Difyの公式サイトまたはGitHubには「Business Contact(商用問い合わせ)」フォームがあり、そこから連絡が可能です。
問い合わせ時には、以下のような情報をまとめておくとよいでしょう。
- 会社名・担当者名・連絡先
- 利用予定のプロジェクト概要(どんなサービスで使うか)
- 商用利用の形態(例:SaaS提供・再販・ブランド変更の有無)
- 想定ユーザー数・ワークスペース数
- 希望する契約時期やサポート内容
Difyの商用ライセンスに関する連絡先は、公式メールアドレスです。このメールアドレスに必要事項を記載して送信すれば、Difyのビジネスチームから折り返し連絡が届き、商用利用の可否や契約プランの提案を受けることができます。
また、公式サイトからも同様に問い合わせが可能で、ページ下部の「Talk to us」または「Business Contact」ボタンをクリックすると専用フォームにアクセスできます。
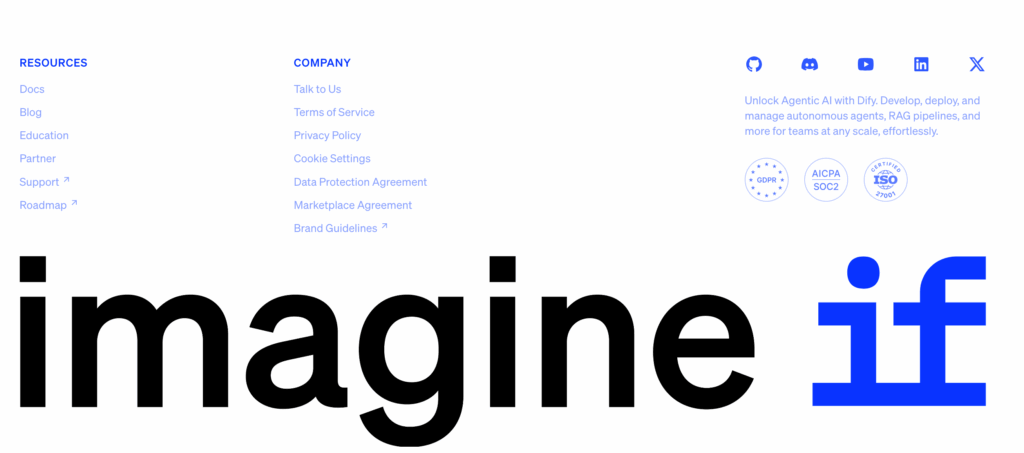
日本国内でDifyの商用ライセンス取得や導入を検討している企業は、TDSE株式会社に相談するのもおすすめ。TDSEは日本語でのサポートに対応しており、契約や技術的な問い合わせにもスムーズに対応してくれます。
3.ライセンス条件の確認・調整
問い合わせ後は、Difyチーム(またはTDSE担当者)から返信が届き、以下の内容についてヒアリングや調整が行われます。
- 必要なライセンス形態(通常・エンタープライズなど)
- 利用範囲(社内利用・SaaS提供・再販など)
- 契約期間・料金の目安
- 技術サポートの有無や範囲
- 商標・ロゴの取り扱い条件
マルチテナント構成や外部提供サービスを予定している場合は、エンタープライズプランを選択しましょう。複数ワークスペースを扱う構成や、他社への展開を想定している場合は必ずこのプランを確認しましょう。
4.契約締結と運用開始
条件がまとまったら、正式にライセンス契約を締結します。契約書には以下のような内容が記載されるため、必ず確認しましょう。
- 商用利用の範囲と制限
- 使用できるワークスペース数や機能範囲
- ロゴ・著作権表記の扱い
- サポート体制(問い合わせ・アップデート対応など)
契約完了後は、合意内容に基づいて商用利用を開始できます。ただし、Dify側のライセンス条件や提供形態が今後変更される場合もあるため、定期的に公式の更新情報をチェックしておきましょう。
Difyの商用利用時の注意点
最後にDifyの商用利用時の注意点を4つ紹介します。利用時にはトラブルを避けるためにも必ず確認・理解しておきましょう。
- 利用規約を定期的に確認する
- 商用利用可否の判断が曖昧な場合は問い合わせる
- 社内ガイドラインを策定する
- セキュリティ対策を実施する
利用規約を定期的に確認する
DifyはApache License 2.0をもとに独自の条件が追加されています。そのため、企業として商用利用する場合は、利用規約を正しく理解し、定期的に確認することが大切です。
利用規約は単なる説明文ではなく、法的な効力を持つ契約書のようなものです。もし記載内容に違反してしまうと、サービスの利用停止や法的措置など深刻な結果につながることもあります。
利用規約はバージョンアップや方針変更によって内容が更新される場合があるため、常に最新の規約をチェックしておきましょう。
四半期に一度は公式サイトのライセンスページを確認し、最新の利用条件を把握しておくと安心です。
商用利用可否の判断が曖昧な場合は問い合わせる
Difyの商用利用に関するルールは、利用形態や構成によって異なるため、どのケースが商用ライセンスの対象になるか判断が難しいことも。自己判断で進めてしまうと誤った解釈をしてしまうリスクがあるため、Difyに問い合わせを行いましょう。
問い合わせ時には、会社の事業内容やビジネスモデル、想定しているユーザー数、ワークスペースの構成、SaaSとして外部提供する予定があるかどうかなど、利用状況をできるだけ具体的に伝えることが大切です。
特にマルチテナント環境を使って複数の企業にサービスを提供する場合や、自社ブランドのSaaSとしてDifyをベースにしたアプリを販売する予定がある場合は、事前に必ずライセンス要件を確認しましょう。
社内ガイドラインを策定する
企業でDifyを導入して安全に使うためには、利用規約を守るだけでなく、社内でガイドラインを作成しておきましょう。ガイドラインは、社員がDifyを日常業務でどう使うかを示すもので、セキュリティの確保と業務効率の両立を目的としています。
たとえば、
- 社内文書に機密情報や顧客データを入力しないルール
- アクセス権限を部署ごとに分けて設定する方法
- 利用可能な機能の範囲
- 禁止行為の明記
などを盛り込みます。また、営業・開発・カスタマーサポートなど部門ごとに異なる利用を想定し、それぞれに適した利用方法や注意点を具体的に記載するのがおすすめです。
定期的に社内研修を実施して従業員の理解を深めたり、利用状況をモニタリングしてガイドラインを見直したりすることも重要です。
セキュリティ対策を実施する
Difyを商用利用する場合、社内外の重要なデータを守るためのセキュリティ対策をしっかり整えておきましょう。特に顧客情報や機密データを扱う企業では、情報漏えいを防ぐためにセルフデプロイを検討するのが望ましいです。
データが外部サーバーに送られることなく社内で完結できるため、安全性が向上します。加えて、不正アクセスを防ぐためにWebAppの無効化やユーザーごとの権限設定、Basic認証の導入などを行い、複数の防御層を持つセキュリティ体制を構築しましょう。
特に金融・医療・製造業などのように高いセキュリティ基準が求められる業界では、対策を徹底することで安心してDifyを運用できます。しっかりとした体制を整えることで、リスクを最小限に抑えつつ、安全かつ信頼性の高い活用ができるでしょう。
Difyのセキュリティに関する対策・方法については以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
参考記事:Difyのセキュリティと安全に使用するためのポイント・対策を解説
Difyの活用を進めるならリベルクラフト
Difyは、自由度の高さに伴い、利用形態によっては商用ライセンスの取得が必要となるケースもあります。
特に、複数の企業やユーザーが同一システムを共有するマルチテナント型のSaaS提供や、Difyのロゴ・著作権表記の削除や改変を行う場合は、事前に公式への問い合わせを通じてライセンス契約を結ぶことが求められます。
本記事を参考にDifyの商用利用をしっかりと確認して、必要であればライセンスを取得しましょう。「Difyを導入したいけれど、設定やセキュリティ対策に不安がある」「使いこなせず効果を実感できていない」という方は、リベルクラフトへご相談ください。

リベルクラフトでは、Difyの導入支援から活用設計、社内教育までを一貫してサポートしています。ノーコードでのAIアプリ開発支援はもちろん、RAG設計やデータ管理体制の整備、オンプレミス環境での安全運用など、企業の状況に合わせた最適な活用方法をご提案。
AI導入の初期段階でつまずかないための伴走支援を行っていますので、「成果につながるAI活用」を実現したい方は、以下のリンクからお気軽にご相談ください。
⇨リベルクラフトへの無料相談・お問い合わせはこちら